小学生の宿題を親がどの程度サポートすべきなのか。宿題は学校で習った内容の定着や家庭での学習習慣を形成するためにあります。宿題に取り組むことで、子どもは自ら考え計画し行動する力を養います。したがって親としては宿題の目的を理解し適切なサポートをすることが求められます。しかしそのサポートがいつまで必要でどの程度行えばよいかは子どもによって異なります。この記事では、小学生の宿題サポートに関するポイントを探っていきます。
宿題のサポートが必要な時期とは?適度な距離感を持つことが大切
低学年のうちは特に宿題のサポートが重要です。まだ時間管理や計画を立てる力が十分でない子どもたちにとって、親が適切に手助けすることで、宿題に対する姿勢や学習習慣を身につけることができます。しかしすべてを親がやってしまうと、子どもの自主性が育ちにくくなるため適度な距離感を持つことが大切です。子どもが自ら宿題を始めようとしている場合は無理に手をだす必要はありません。逆に子どもがどのように宿題に取り組んでいいかわからない場合や、集中力が続かない場合は計画を立てる方法やタイムマネジメントを一緒に考えるなど、段階に応じたサポートを行うことが重要です。
いつまで?宿題のサポート
宿題のサポートが必要なくなる時期には個人差があります。子供の発育には違いがありますし早生まれなども影響します。目安としては、子どもが自分で宿題を終わらせ時間管理ができるようになるまでを考えるとよいでしょう。中には自分でスムーズに進められる子どももいれば、苦手な教科や問題に直面してつまずくことが多い子どももいます。そういった場合は、時折チェックを行い、どこでつまずいているのかを一緒に確認してあげることで、適切なサポートが可能となります。
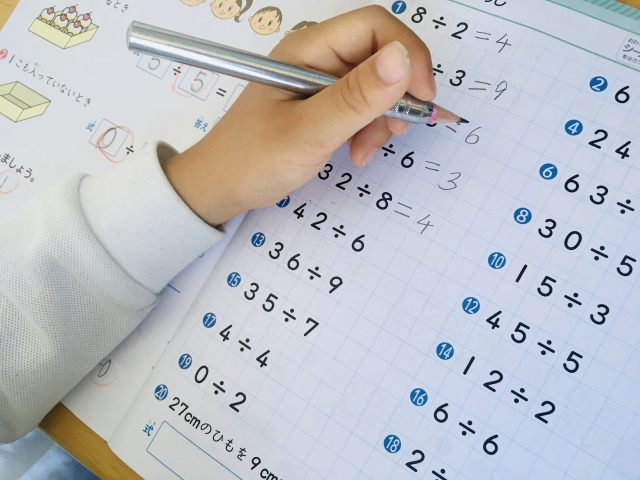
サポートの際に避けるべき行動
宿題のサポートにおいて気をつけたい点として、保護者が無意識のうちに子どものやる気を削ぐ行動を取ってしまうケースがあります。以下のような行動は避けるようにしましょう。
1. 完璧なチェック
子どもの宿題に対して完璧さを求めすぎることは逆効果です。例えば、字がきれいでないからといって何度も書き直させるなど、過度に神経質になると子どもが宿題自体を嫌がるようになってしまいます。また漢字のミスを繰り返してしまう場合でも怒ったり執拗に直させるのではなく覚えやすい方法を提案したり問題をリストアップして一緒に練習するなどの工夫が求められます。子供相手ですからある程度のミスは許容して子どもの成長を見守ることが大切です。
2. 感情的に怒る、怒鳴る
宿題に取り組まない子どもに対して感情的に怒ってしまうことも、避けるべき行動のひとつです。やらされている感が出てしまうとモチベーションが低下する可能性があります。さらに算数や国語のミスを指摘する際に感情的になってしまうと、子どもは「勉強ができない自分はダメだ」と自己否定に陥りやすくなります。幼少期は根拠の無い自信に満ち溢れているくらいがちょうどよいのです。
3. 他の子どもと比較する
他の子どもと比較することも、非常に避けるべき行動です。お兄ちゃんは~○○君は~といった発言は、子どもの自己肯定感を低下させてしまいます。そうすると自分に自信を持つことが難しくなる原因となります。宿題はあくまで個々の成長に応じて進めるものなので、他の子どもとの比較は不適切です。子どもの進捗を見守りながら、個々の成長を大切にしてあげましょう。
親は宿題とどう向き合うべきか
では、どのように宿題をサポートすることがベストなのでしょうか?以下のポイントを意識してみましょう。
1. 自主性を育てる
子どもが自ら宿題に取り組むことを促すことが大切です。子ども自身に宿題の進め方を申告させることで、自主性を育てることができます。
2. 定期的なチェックをしてあげる
宿題が終わったら時など保護者が最終的なチェックを行うことで、子どもの学習状況を把握することができます。子どもが一人で宿題を進められる場合でも定期的に学習の進捗を確認することが、長期的な学力向上につながります。投げっぱなしにせず少し確認してあげましょう。
3. 必ず褒めてあげる
宿題を終わらせたことに対して、適切なフィードバックを与えることも重要です。たとえ完璧でなくても、「よく頑張ったね」と声をかけることで、子どもは宿題をすることでほめてもらえる!うれしい!という意識を持つことができます。ポジティブなフィードバックは、学習意欲の向上に繋がります。
まとめ
小学生の宿題はただの学習内容の確認だけでなく子どもの自主性や時間管理能力を育てる重要な要素です。保護者として適切なタイミングでサポートを行い過度に介入しないことが子どもの成長を助けるポイントとなります。怒るのではなくポジティブに関わり自主的に取り組めるような環境を整えてあげることが、最終的には子どもの学習意欲を高める一歩となるでしょう。

