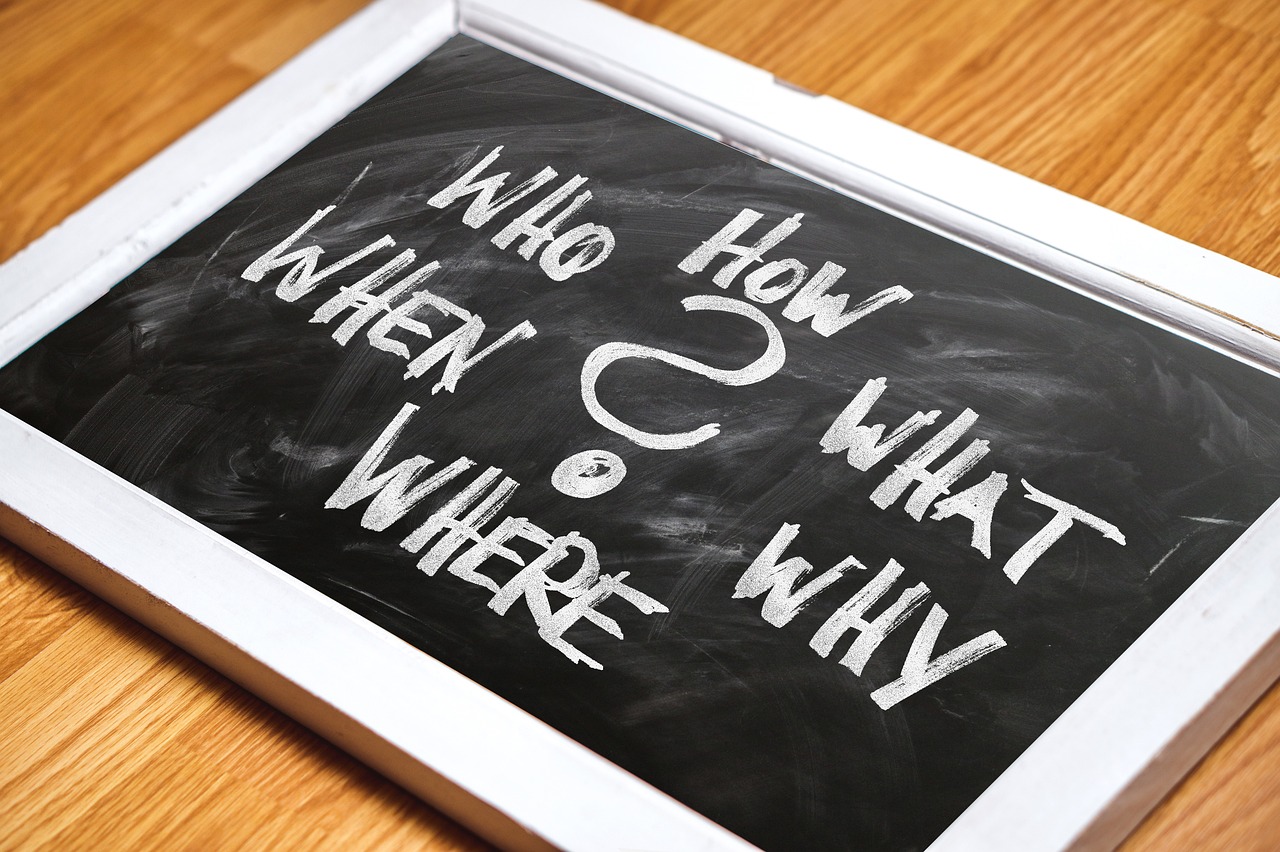2025年度の首都圏中学入試における動向を探ると、いくつかの注目すべきポイントが浮かび上がります。受験者数は2024年度と同程度の規模を維持し、過去最高水準に達した2024年の勢いが続くことが予測されています。しかし、その裏側には難関離れとも呼ばれる現象が見られます。これにより、難関校や上位校では志願者数がわずかに減少する傾向があります。受験生や保護者が背伸びをしてまで挑戦することに疲弊している様子がうかがえますが、それでも増加傾向にある学校や入試回には注目が集まります。
難関校志向の減少と中堅校の台頭
難関校の志願者数が横ばいまたは微減となる一方で、偏差値50台から40台の中堅校が勢いを増しています。しかしすべての学校が等しくその恩恵を受けているわけではありません。人気を集める中堅校の多くはには当然理由があります。特色ある教育や進学実績、面倒見の良さなどで差別化を図っています。受験生や保護者にとって、難関校だけではなく自分たちの目指す将来像に合致する学校が増えている点は大きな魅力といえるでしょう。
中学受験は始めた時期が遅いなどの理由で偏差値が上がり切らないケースもあります。そういった場合は無理に難関校にチャレンジし散るより、また受かっても秀才にかこまれ深海魚生活となるよりも自分のレベルに見合った学校に行くほうが幸せだったりします。
入試内容の変化と「英語導入元年」
2025年は「英語導入元年」とも呼べる年です。多くの学校で英語を重視した入試が導入され、筆記試験や面接、英語資格の反映が増加しています。特に豊島岡女子学園では、英語資格を考慮した算数との2科入試を導入するなど、新たな取り組みが注目されています。この動きは、公私間の教育格差を浮き彫りにしたコロナ禍以降の流れを反映しているとも考えられます。
英語は大学受験の時に多くの受験生が壁としてぶち当たります。とくに高校受験と違い英語が無いことがハンディキャップとなってしまい中高一貫のメリットが損なわれるケースもあります。
近頃は公立校の教育水準も向上しています。1人1台のタブレット導入が進み、以前と比べて学校環境が改善されていることから、私立校との極端な差は感じられなくなっています。それでもなお、私立校の受験率が上昇しているのは、私立校や国立、公立一貫校への教育的期待が高まっているためです。
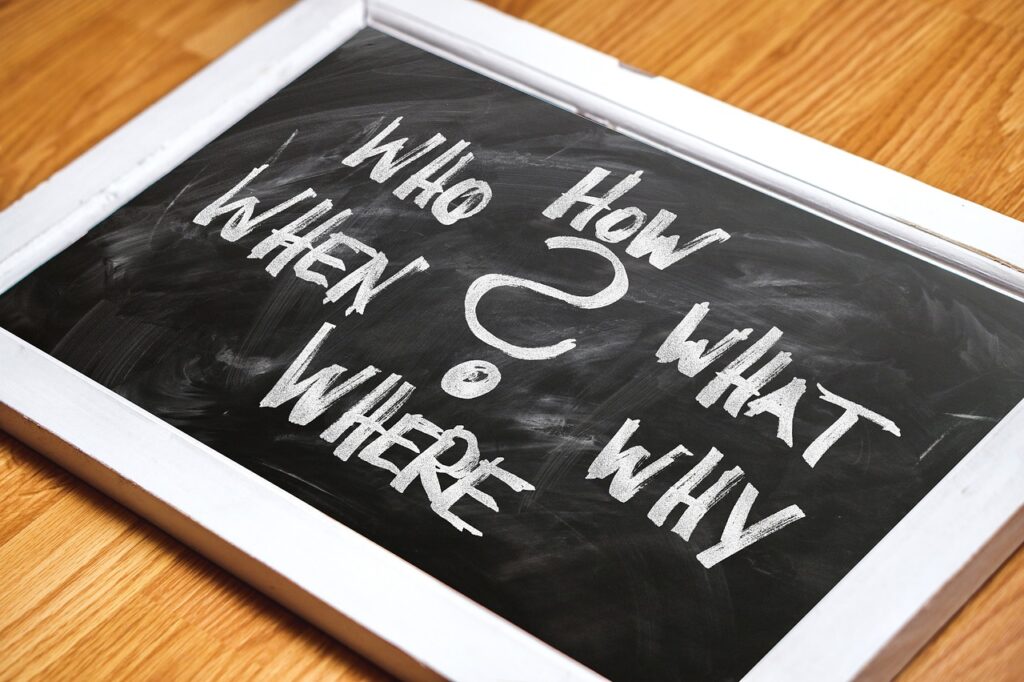
地域別の動向と少子化の影響
首都圏全体では小6人口が安定していますが、東京を除く地域では減少傾向が続いています。特に千葉、神奈川、埼玉では減少率が高く、各学校は対応を迫られる状況にあります。その一方で、都心部では依然として受験率が高いままで、教育の質を重視する家庭が私立中学を選ぶ傾向が強まっています。
埼玉県では、栄東が日程を柔軟化し、多様な受験機会を提供することで、さらに多くの受験生を集めることが予想されています。開智学園も、新校の開智所沢を含め、多様なコース設定で注目を集めています。これにより、2025年度も開智学園と栄東が受験生から人気を集める見込みです。
千葉県では、市川が引き続き安定した人気を誇っています。また、光英VERITAS(ラテン語で真理を指す)、芝浦工大柏、専修大松戸といった学校も独自性を発揮し、志願者を増やしています。
埼玉千葉はお試し受験として人気を博しますが実際に通う生徒はあまり多くない傾向にあります。また千葉と埼玉で受験生を喰いあうことはあまりなく東京の多摩地域に住んでいる人は埼玉地域、都市部や神奈川は千葉地域というすみわけが多いです。
実際問題東京の多摩から千葉への通学は非現実的ですし、神奈川から埼玉、千葉もかなり無理があります。このあたりが大学受験とは大きく異なる点でしょう。
最難関校と附属校の動き
男子最難関校では、筑駒が昨年度の通学範囲拡大の影響で受験者数を増加させました。しかし、地域によっては筑駒と開成の両方に合格して開成を選ぶケースも見られます。これは、通学時間や校内の規模感、教育内容の違いによる選択が影響しています。筑駒は少人数で手厚い教育を提供する一方、開成は生徒数が多い分、多様な活動機会を提供しています。
大学附属校では、慶應普通部が入試結果の公表を始めたことで志願者数を増やしています。一方、麻布や武蔵では、附属校人気や中堅校の面倒見の良さに押されて志願者が減少しています。それでも、最難関校の成績上位層の水準は安定しており、志願者の減少は主にチャレンジ層の減少に起因しています。
麻布や武蔵などの学校は学校でそこそこの成績を取っていても推薦で有名大学に行けるわけではありません。エスカレーター持ちの早慶MARCHには分が悪くなっていているのも事実です。ただし御三家に受かるようなバイタリティーがあればMARCHにはまず受かることから多くの場合中学受験塾としてはどう偏差値帯の付属校に行くのはもったいないという傾向にあります。
志望校選びの多様化
2025年度入試では、受験生や保護者が志望校を選ぶ際の基準がさらに多様化しています。たとえば、海外大学進学を視野に入れた私立校のプログラムが注目されています。これは、文部科学省のカリキュラムに縛られる国立校では難しい対応です。私立校の柔軟な教育内容が、進学実績や教育方針を重視する家庭からの支持を集めています。
まとめ
2025年度の首都圏中学入試は、志願者数の規模維持、「難関離れ」による中堅校人気の高まり、英語導入元年としての入試内容の変化など、多くのトレンドを抱えています。少子化や地域ごとの人口減少が進む中でも、私立中学の人気は依然として高く、家庭ごとの教育ニーズに応じた多様な選択肢が提供されています。志願者が増える学校や新たな試みを導入する学校が注目される一方で、従来の人気校も進化を続け、受験生を惹きつけています。これらの動向を踏まえた入試準備が、受験生にとって大切になるでしょう。