算数の文章題を克服するために
1. 算数の文章題はなぜ難しいのか?
学年が上がるにつれ、算数の文章題は難しくなっていきます。「計算は得意」「算数は好き」というお子さんでも、文章題になると点数が取れないケースは珍しくありません。その理由の一つとして、「国語の読解力」が関係していることが挙げられます。
算数の文章題は、短い文の中に重要な情報が凝縮されています。例えば、「りんごが3個あります。さらに2個買いました。全部で何個になりますか?」という問題では、与えられた数値を整理し、「3 + 2 = 5」という式を立てる力が求められます。そのため、不要な情報をそぎ落とし、的確に理解する力が必要です。しかし、文章を正確に読み取る力が不足していると、どのように解けばよいのかが分からず、問題を前にして立ち止まってしまうこともあります。「3 + 2 = ?」という問題が与えられていれば誰でも簡単に5と解くことができますがまずどんな式を立式すればいいのかわからなければ解くことができません。当然学年を増すごとに難易度は上がっていくため立式そのものが難しくなっていくのです。
2. 文章題を解くために必要な力
文章題を解くためには、以下のような力を身につけることが重要です。
1. 国語力(読解力)
- 文章を正確に読み取る力。
- 言葉の意味を正しく理解する力。
- 問題の意図を正確に把握する力。
算数の計算が得意という子供でも文章題になったとたんに成績がガタ落ちなんてことはザラにあります。そういった子は国語の成績が悪いケースが多いです。そもそもの文章を読み解く力がないため立式に至らず得意な計算の前に失点してしまうことが散見します。
2. 論理的思考力
- 条件を整理し、推理する力。
- 記述された情報を関連付ける力。
- 計算する順序を考え、計画的に解く力。
ただし小学生時点で論理的思考力を高めることは困難です。そのためこれを身に着けようと子どもに無理をさせる必要はありません。論理的思考力はつけようと意識するよりも算数の問題をしっかり理解して解いていると自然と身につく後天的なものとして考えましょう。大人になっても論理的に考えることの出来てない人は恐ろしい程多く、そういう人は自分のロジックが飛躍して結論にたどり着いていることにすら気づきません。算数や数学をしっかりと勉強しているとそうした飛躍を起こせば数式が成り立たなくなり×になってしまうということを解きながら学んでいきます。ロジカルシンキングともいわれビジネス面で必須であることから社会人になって必死に身に着けようとする人が多いこの能力ですが実は小学生のころからどんな勉強して来たかで練度が違います。
3. 基礎計算力
- 四則演算を正確に行う力。
- 計算ミスを減らす力。
- 見直しの習慣をつけることで、計算ミスを防ぐ。
- 問題を解いた後に、自分で別の方法で解き直して答えを確認する。 四則演算を正確に行う力。
- 計算ミスを減らす力。
この力は純粋な計算力のため中学受験には効果がないと言われる公文式などでも鍛えることができます。小学生4年生以降は公文式を中学受験のためにやる必要はありませんが低学年のうちは四則演算の演習をたくさん積める公文式や学校の宿題も役に立つことでしょう。
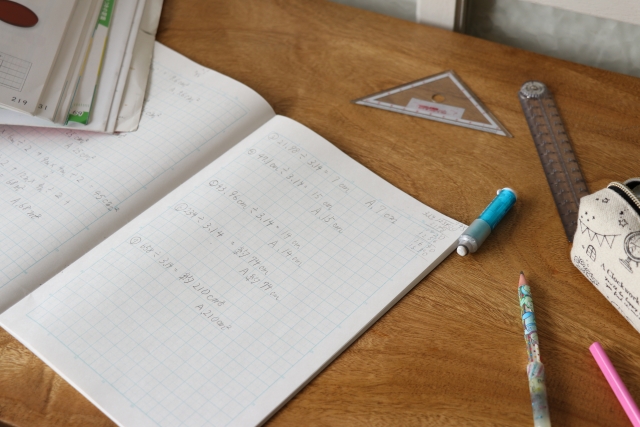
3. 文章題を得意にするための方法
文章題が苦手なお子さんには、いくつかの共通点があります。例えば、「問題文が長いと途中で何が言いたいのかわからなくなる」「登場する数字を適当に計算してしまう」「式を立てること自体に苦手意識を持っている」などです。このような問題に直面するお子さんは、単純な計算問題では高得点を取れるのに、文章題になると急に間違いが増えてしまうことがよくあります。
1. 日常生活で経験を増やす
実は算数の文章題の多くは、日常生活に根ざした内容です。例えば、買い物をするときに「この商品を2つ買ったらいくらになるか?」などの問題を一緒に考えることで、算数を身近に感じることができます。また、宿題をするときに、お子さんが興味を持ちやすい題材で文章題を作り直してみるのも効果的です。
2. 音読する習慣をつける
文章題を解く際に、条件を読み飛ばしてしまうことがよくあります。そのため、自宅で学習する際は、1文ずつ音読しながら解く習慣をつけましょう。音読することで、条件の読み落としを防ぎ、問題の意図を正しく理解できるようになります。音読は算数以外でも非常に効果のある勉強法です。自分の声を自分で聞くというのは覚えることに一役買ってくれます。国語は勿論、理社の暗記部分でも音読するだけで暗記できる量もクオリティも桁違いです。小学校の課題で音読課題が出るものしっかり効果があるということですね。
3. 文章を絵や図に表す
文章題が苦手なお子さんの中には、「文字情報だけでは状況を想像できない」というケースが多くあります。そのため、線分図や簡単なイラストを使って、問題の状況を可視化すると理解しやすくなります。特に、「速さの問題」や「割合の問題」では、図に表すことで解法が明確になります。この図示する力は理科の計算分野でも大きな力を発揮します。とくに物理学の分野は図示の能力が大きく得点を分けます。理科の計算範囲は中学受験時点ではそこまで大きくありませんが入学後や理系進学する場合は非常に必要な能力になります。
4. 知らない言葉を調べる習慣をつける
文章題の中には、普段あまり使わない言葉が含まれていることがあります。例えば、「時速」「秒速」「売上」「利益」などの言葉の意味を正しく理解していないと、正しい式を立てることができません。わからない言葉が出てきたら、その都度調べる習慣をつけましょう。
5. 問題を解くときにポイントを押さえる
文章題の解答に必要な条件を的確に見抜くために、以下のような方法を実践しましょう。
- 重要な言葉に印をつける 「が」「の」「を」「に」「へ」「と」「より」「から」「で」「や」などの格助詞は、文章の意味を整理するのに役立ちます。これらの言葉が出てきたら印をつけ、情報を整理しながら読むようにしましょう。文章題を解くうえで意外とやりがちな読み間違いです。読み間違いが治るまでこれらのワードはチェックをつけながら読むのがいいでしょう。国語でも必要な能力のため一石二鳥です。
- 間違い直しを徹底する 解いた問題の間違い直しをするときに、見落としていた部分に線を引くことで、同じミスを防ぐことができます。「なぜ間違えたのか?」を分析する際には、①問題文を再読し、どの情報を見落としたのかを確認する、②自分の立てた式や計算手順を見直し、どこで誤ったのかを特定する、③正しい解法と比較し、どのように考えればよかったのかを整理する、という手順を踏むことで、次に同じような問題が出たときに正しく解けるようになります。
4. 文章題を得意にするための学習習慣
1. 本を読む習慣をつける
読書をすることで、自然と文章を読み取る力が養われます。特に、物語や説明文などの異なる種類の文章を読むことで、文章題を理解する力が向上します。ただし小学校6年にもなるとあまり読書している暇すらありません。低学年のうちから読みやすい本でかまわないので活字になれる練習をしましょう。
2. 問題を整理する習慣をつける
算数の文章題では、「何が求められているのか」「どの情報が必要なのか」を整理する力が必要です。これを鍛えるために、問題文の内容を紙に書き出して整理する練習をしましょう。
3. 「考えること」を楽しむ
文章題は、論理的思考力を鍛えるための良いトレーニングです。「パズルを解くように楽しむ」「ゲーム感覚で挑戦する」など、興味を持てるような工夫をすると、苦手意識を克服しやすくなります。
まとめ
算数の文章題が苦手な理由の多くは、読解力や論理的思考力の不足によるものです。しかし、日常生活の中で経験を増やしたり、音読や図解を取り入れたりすることで、文章題を解く力は確実に向上します。
すぐに実践できるステップとして、以下の方法を試してみましょう。
- 日常生活の中で計算をする機会を増やす(買い物や料理など)。
- 文章題を音読し、問題の条件を正しく理解する。
- 線分図や絵を描いて、状況を視覚的に整理する。
- 間違えた問題の分析を行い、なぜ間違えたのかを理解する。
- 楽しみながら取り組める方法を見つけ、お子さんに合った学習スタイルを確立する。
これらを習慣化することで、文章題への苦手意識が減り、確実に解く力が身につきます。

